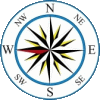2017年10月15日
「調理ロボ」は飲食店の人手不足を救うか 効率的でおいしい実力
外食業界で「調理ロボット」が存在感を増している。高齢化や人手不足が深刻化する中で、作業の効率化は喫緊の課題。さらに2020年の東京五輪を控え、業界関係者からは「ボランティアに人手をとられてしまうのでは」と不安の声もあがる。古くて新しい日本の「調理ロボ」はこの危機を救うのか。活用の現場をたずねた。(週刊エコノミスト編集部/Yahoo!ニュース 特集編集部)
妻の腕を支えた炒飯ロボ
「炒飯ください」と告げると、店員が中華鍋に卵と白米を入れ、お玉で軽くかき混ぜはじめた。見慣れた風景だが、次に店員が手を伸ばしたのが「3本のツメ」がついたアーム(腕)だった。鍋が置かれた調理台のボタンが押されると、ツメが、鍋の動きに合わせて具をかき混ぜ始めた。
途中、塩こしょうなどを店員が入れていく。できたての炒飯は、火が良く通ってあつあつ、パラパラだ。
ツメを3本にすればコメが飛び散らずもっとも美味しくなると分かるまで試行錯誤が続いた(撮影:週刊エコノミスト編集部)
千葉県松戸市の「ラーメンショップ八柱店」が、三栄コーポレーションリミテッド(横浜市港北区)の炒飯ロボット「鉄腕炒レンジャー」を導入したのは2006年。店主の高栖寿一さん(72)、妻の裕子さん(73)、長男の一博さん(41)の家族で経営する。
客の多くが「半チャン・ラーメン」を頼む。「私が麺をゆで、炒飯は妻が作っています。中華鍋をあおり続けるのは大変で、11年前に機械の導入を決めました」(寿一さん)
炒レンジャーの動きはカウンターごしに良く見える(ラーメンショップ八柱店)(撮影:週刊エコノミスト編集部)
中華のプロの動きを分析
炒レンジャーを開発した同社は、外食店の厨房の設計・施工を得意とする板金工場として63年前に創業した。
25年前に販売開始した自動ゆで麺機「マルチ・ボイル」が人気商品となり、麺脱水機「ヌードルセッター」と合わせ、すでに5000台以上の納入実績があった。「個人経営の中華料理店には、高齢となり中華鍋を振るのが大変だからお店をたたむ、と悩んでいる経営者が多かった。そこで炒飯を作る機械を考えました」と同社の深澤及社長はいう。実際、中華鍋の重さは1.5キロ、具材が入ると2キロ近くなる。
「高齢で鍋を振るのが大変という方に使ってもらいたい」と三栄コーポレーションの深澤及社長(左)と岡山英一係長(撮影:週刊エコノミスト編集部)
炒飯ロボットの開発には、横浜中華街の有名店からプロの調理師も呼び寄せた。調理作業の様子を動画で撮影し、念入りに分析したところ「1秒に2.5回、楕円(だえん)運動で鍋をあおるのが最もおいしくできる」と気づいた。
しかし、鍋をあおるだけではダメだった。プロは、お玉を使ってチャーハンをかき混ぜていた。そこでお玉代わりに3本のツメの付いたアームを考案した。3本のツメを鍋の上に載せるように配置すると、「お米が飛び散らずパラパラにできあがる」と分かったという。
炒レンジャーは03年に完成した。1回の調理時間は3分。2~3人前の炒飯を作ることができる。1時間で最大60人前だ。「機械は炒めるところだけで、味付けはお店独自のものにできます。火力も調整できるので、野菜炒めに使っているお店もあります」と厨房事業部係長の岡山英一さん。
価格は123万円と安くないが、「いまは月2万4000円のリースを始めました。自動ゆで麺機とセットでも3万7800円。人手不足と高齢化に悩んでいるお店に販売していきたいですね」(同)という。
炒レンジャーでつくったあつあつパラパラの炒飯(ラーメンショップ八柱店で)(撮影:週刊エコノミスト編集部)」
これまでに250台を納入しており、海外向けでもシンガポール、米国、豪州など10カ国以上に納入している。香港ではミシュランの星を取った店が導入し、「炒飯にとどまらず、炒め物など、さまざまな中華料理を作っています」という。
回転寿司の市場拡大を支えた「シャリ握りロボ」
「これ、食べられるの?」。1983年、日本橋三越本店が開催したロボットが握ったすしをふるまうイベントで、最初にすしを見た客はそう言い放った。だが、1人の客が興味を示し「おいしい!」と言ったことから、多くの来場者が試食するようになった。
これが81年に鈴茂器工(東京都練馬区、ジャスダック上場)が完成させた「シャリ玉ロボット」が普及するきっかけになった。
元々、鈴茂器工は和菓子の製造機械の会社だったが、70年に始まったコメの減反政策を受けて、「コメ消費を拡大できれば減反の流れに歯止めをかけられる」と、創業者の鈴木喜作氏(故人)が76年に米飯加工機械の開発に乗り出した。
鈴茂器工のシャリ玉ロボットは軍艦巻きにも対応できる(撮影:週刊エコノミスト編集部)
当時、外食のなかでもすしは高嶺の花。しかし「すしロボット」を開発し、価格が下がれば、すしの外食は一般的になり、コメの消費量も増える」と鈴木氏は考えた。
当初は、すし職人から「仕事を奪う」という反発もあったそうだが、「機械で作った新たな市場を作りだそう」(小根田育冶<おねだ・いくや>会長)と開発を断行。時価商売の業界に粘り強く、コスト感覚や経営の効率化を説いてまわり、それが回転ずしの普及と軌を一にした飛躍につながった。
「日本のお米の消費量を増やしたい」という鈴茂器工の小根田育冶会長(撮影:週刊エコノミスト編集部)
すしロボットの基本的な工程は、まずお櫃(ひつ)にあたる容器でコメを「ほぐし」、左右に並んだ車輪の間を通しながら1カン単位に「計量」し、シャリの形に「握る」パーツに落とし込む。
この基本の3工程は現在も同じだが、性能は少しずつ向上させていった。「ほぐす」工程は、シャリに空気を含ませてふんわりと仕上げるために欠かせない。
温かくふんわりしたシャリは1時間で最高4800個つくれる(撮影:週刊エコノミスト編集部)
職人の握るシャリより「フワリ」
すし職人は、お櫃の中のシャリを手でほぐすが、これはかなり握力がいる作業だ。そのため腱鞘炎になる職人も多い。かといって、機械でシャリを攪拌(かくはん)するとコメを練ってしまい、食味が落ちる。
小根田会長は、羽根でコメを攪拌すればフワリとほぐせると気づいた。「科学的にも人間が握ったシャリよりも機械が握ったシャリの方が多く空気を含んでいることが分かっています」
1カンごとに分ける工程も、以前はステンレス製のカッターで切り分けていたが、コメの断面がカットされ、切り口から水分が蒸発し、皿にもくっつきやすい。そこでプラスチックの櫛型の部品が左右からかみ合わせる形にしたところ、食味がさらに良くなった。
シャリが乾燥せずお皿にもくっつかないように切り分けるくし形の部品にはいまも技術特許がついている(鈴茂器工のシャリ玉ロボットの部品)(撮影:週刊エコノミスト編集部)
難しいのが、シャリを「握る」工程だ。以前は、シャリとなるコメのまとまりを、上部と左右の3方向から押していたが、現在はすし型の容器に落としてやさしく成型する。容器の素材もコメがくっつかないよう、哺乳びんの口と同じ「シリコン素材」を採用した。こうしてできたシャリは、口の中で程よくほぐれる。
この「ほぐす」と「握る」の部分の技術特許はすでに切れており、他社も参入しているが、それでも鈴茂器工のすしロボットは、これまでの実績、「トータルのすしのクオリティーの高さ」(都内すし店店主)からいまもシェア70~75%を維持している。近年は、「軍艦巻き」「太巻き」「細巻き」「カリフォルニア巻き」にも対応する。
さらに握るスピードは職人より速い。シャリ玉ロボットの1号機の頃は、1時間当たり1200個だったが、最新型は実に同4800個を握ることができる。
回転ずしはいまや全国に3000店。日本フードサービス協会によると2016年の外食産業の市場は約25兆円と前年比で0.1%増の伸びにとどまるが、回転ずしを含む寿司店は、前年比4.4%増の1兆5000億円にまで拡大した。機械は1台100万円から。機械化で人件費を削減できた結果、一皿2カンで100円のすしが実現したわけだ。
鈴茂器工は現在、約70カ国に輸出し、海外売上比率は22~23%に達する。これを早期に100カ国、30%を目指すという。
カウンターごしで食べる人の前ですしを握ることもできるおひつ型のシャリ玉ロボットもある(撮影:週刊エコノミスト編集部)
小根田会長は2000年代はじめに海外のすしブームを受けて米国に飛んだが、シャリの不味さに落胆。「本物のすしを普及させなければブームは続かない」と、06年にカリフォルニア州トーランスに現地法人も設立した。
すしロボットの市場規模は年間180億~200億円、小根田会長は世界展開で「10倍に拡大させることも夢ではない」と語り、機械を売り込む営業だけではなく、すしの作り方の指導などソフト面の対応を組み合わせて、海外のレストランでも日本のコメを使うよう働きかけているという。
肉をつぶさず職人のように串を刺す
JR横浜線・相模原駅からバスで5分。住宅街の一角に「串刺機のパイオニア」といわれるコジマ技研(神奈川県相模原市)がある。
従業員わずか15人のこの会社が日本のスーパーやデパート、コンビニで売られている焼き鳥やおでんを支えている。
焼き鳥の肉に串を刺す作業は、熟練した職人でも1時間で80~90本が限界だ。これをコジマ技研の串刺機を使うと、小型の機械で1時間に300~500本、工場向けの大型機械なら最速で1万本も刺せる。
串刺機で刺せば鳥肉がくるくる回ることもない。コジマ技研の小嶋實会長(左)と小嶋道弘社長(撮影:週刊エコノミスト編集部)
同社は元々、自動車部品や家電の製造工程で使われる産業用の省力機械を作っていたが、創業者である小嶋實(みのる)会長(84)は75年に串刺機の開発を決意。当時、焼き鳥の串刺機を作るメーカーは多数あったが、焼き鳥店や食肉メーカーからは相手にされていなかった。肉に正確に串を刺すことができないなど機械の性能が低かったのだ。
そこで小嶋会長は、「いかに肉をつぶさずに押さえる型を作り、職人のように串が刺せるか」に注力、77年に初号機を完成させ、79年には大手居酒屋チェーン店へ、初号機を納入する。
飛躍のきっかけは、85年に大手食肉メーカーから「アメリカンドッグ」の自動生産ライン(全27ライン)の串刺しの工程を担当し、串刺機の技術的な評価を確立したこと。大手ハムメーカーから焼き鳥の生産ラインも受注した。
焼き鳥に加え、もう一つ同社の成長を支えたのが「おでん」だ。2000年、大手コンビニチェーンから三角形のこんにゃくを先端に刺したおでん串を製造できる機械を頼まれた。
コンビニ大手の要望はこうだ。「おでんの容器に穴を空けてはいけないので、こんにゃくを突き破らずに串を刺し、さらに30回振っても串から抜け落ちず、こんにゃくが、くるくる回らないようにしてほしい」
大手居酒屋チェーンに納入したコジマ技研の串刺機の初号機タイプはネットオークションで買い戻したという(撮影:週刊エコノミスト編集部)
ほかの串刺機メーカーであれば尻込みするような難易度の高い要望であったが、焼き鳥の串刺機で技術を磨いたコジマ技研にはお手ものだった。
同社の串刺機は、鳥のもも肉からナンコツ、レバ、つくね、豚のタン、ハツ、カシラなど、堅いものから柔らかいもの、さまざまな形状や大きさの肉をパレットというプラスチック型に配置し、上押さえ(うわおさえ)という金属製の型で押して串を刺す。
プラスチックの型にもノウハウがある(撮影:週刊エコノミスト編集部)
「肉をつぶさず、肉同士のすき間も作らず、波打つように串を刺して、肉がくるくる回らないようにする型にこそ技術の真髄があります」と小嶋会長。
2003年末、中国で鳥インフルエンザが発生した。すると、今度は食材の国産回帰が始まり、串の状態で輸入される外国産の鶏肉より、国産の手作りが好まれるようになった。しかし、職人は不足している、ここでまた串刺機のニーズが増えた。「これまでに累計で3000台以上は納入しています」と小嶋会長の息子で、社長を務める小嶋道弘さんは語る。
5時間の仕込みが2時間に短縮
3年前、小田急線東海大学駅から徒歩10分の線路沿いに焼き鳥店「呑喜」を開業した合田淳さん(28)は今年6月、このコジマ技研の串刺機を約160万円で導入すると決めた。それまで5時間かかっていた焼き鳥300本の仕込みが2時間に短縮された。「その分はお店を宣伝するSNSや他の仕込みの拡充が行えるようになり、売り上げは3割アップしました」と合田さん。
店長を任されている東海大学3年生の犬飼青空さん(20)は、「味はまったく手打ちの時と変わりません。むしろ機械になって形のばらつきがなくなり、焼きやすくなりました」と喜ぶ。お店は40席で満席、一人7本も食べれば300本はすぐになくなる。お土産もある。用意した焼き鳥がすべてなくなっても「5分で作れるので助かってます」(犬飼さん)。
串刺機を入れて「焼きやすくなりましたよ」と神奈川県秦野市の居酒屋「呑喜」の犬飼青空店長(撮影:週刊エコノミスト編集部)
外食産業を魅力ある職場にできるか
三栄コーポレーション、鈴茂器工、コジマ技研の3社に共通するのは、人手不足や高齢化に困る飲食店を救済しているところだ。
現実のデータは、これらの機械のニーズが今後確実に増える、という未来を示しているようだ。
厚生労働省の統計によれば、1996年に16万9000人だった全国の飲食店の調理師の就業者数は、06年には10万9000人、16年には6万9000人と実に20年前から10万人も減少している。
この調理師急減の背景の一つは、大手外食チェーンが経営効率化のために編み出したセントラルキッチン方式、つまり工場で半完成品にした食材をお店で温めるだけ、といったアルバイトでも調理できる方法の普及がある。
調理師の就業者数は減り続けている(イメージ:ペイレスイメージズ/アフロ)
もう一つは、調理師そのものを目指す若者が減少し続けていることだ。ある大手調理師学校の校長は、高校卒業後、調理専門学校に行く学生がこの10年で激減し、「いまも徒弟制度が残り、技術の習得に時間がかかる日本料理の人気がとくに落ちています」と話す。75年の調理師免許交付数は約10万8000だったが、14年は3万8000に激減、少子化以上に調理師を目指す若者が減っている。
日本フードサービス協会の石井滋業務部長は、「外食産業の現場を魅力あるものにしないと、人手不足はさらに深刻になります」と指摘する。協会の2016年の調査によると、アルバイトを含めた従業員数が150人から2000人の飲食店28社にアンケートしたところ、充足率つまり実際の運営に必要なホールや調理スタッフをどれくらい手当できるか聞いたところ、60~80%と答えた飲食店が全体の7割を占めた。つまり、実際の店舗運営で10人必要なところを6~8人で回しているのが現状なのだ。
さらには、2020年の東京五輪では総計で9万人以上がボランティアとして稼働するという。開催時にはより深刻な人手不足が予想される。
石井部長は「働き方改革や時短といいますが、職場環境をどう改善するか、具体的には従業員同士のコミュニケーションと研修の充実、未来を描けるビジョンを提示することが重要」という。調理ロボットに職を奪われるという懸念より、「外食産業の調理の現場をいかに魅力あるところにするかが課題」(石井部長)というわけだ。
調理の現場を魅力あるものにすることが課題に(イメージ:ペイレスイメージズ/アフロ)
今年8月、焼き鳥チェーン大手の鳥貴族が28年ぶりとなる値上げを決め、メディアを賑わせた。全品280円均一という価格をついに298円としたのだ。理由は国産食材の仕入れ価格高騰と「中長期的な人件費の上昇」だ。実は鳥貴族は焼き鳥の手打ちにあくまでこだわり、「機械を導入する予定はありません」(鳥貴族)という。
インターネット上には、時給950~1000円の「串打ちスタッフ募集」が掲載されない日はなく、慢性的な人手不足が値上げの背景にあることを伺わせる。
秦野の焼き鳥店「呑喜」の犬飼店長は、機械で焼き鳥を仕込みながら備長炭で焼き、アルバイトにお土産用の焼き鳥の焼き方を指導しながら串刺機を使いこなしていた。
調理ロボットを縦横無尽に使いこなし、時間と心に少しゆとりを持った飲食店の現場に、日本が直面する人手不足と高齢化を解決するカギは隠されているかもしれない。
|
|